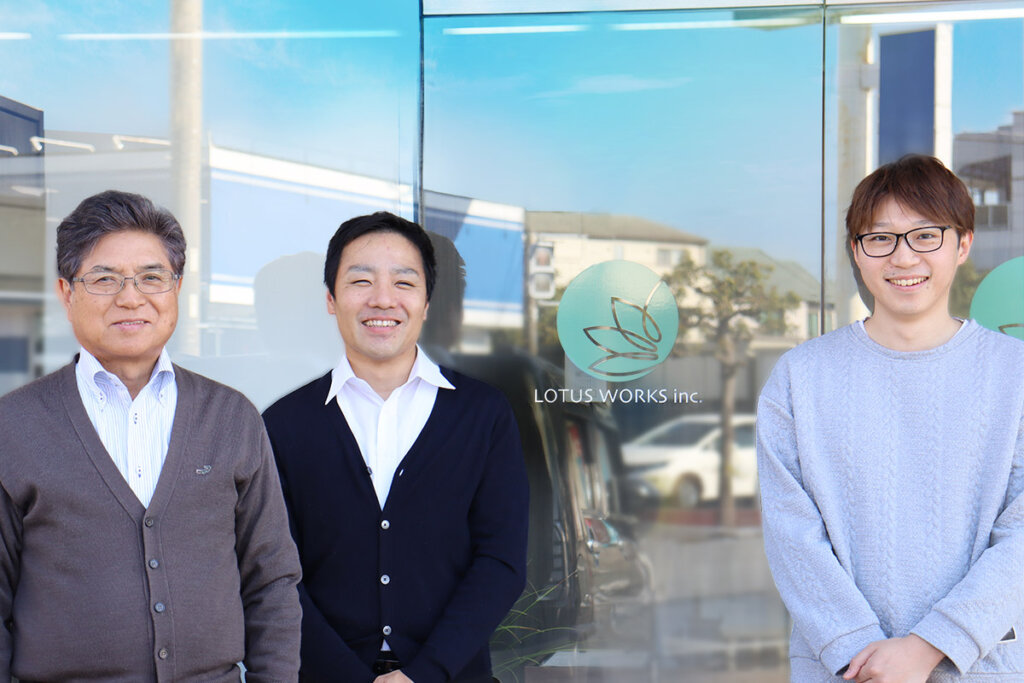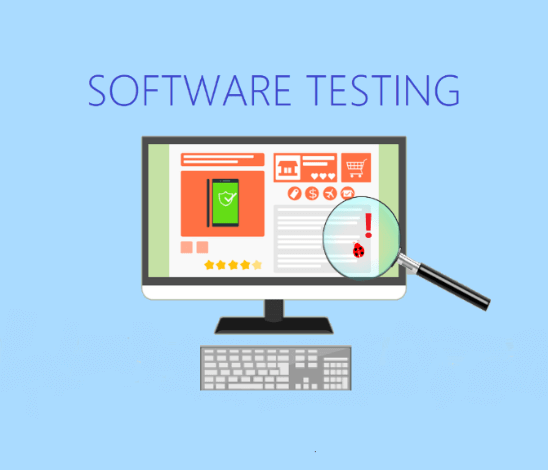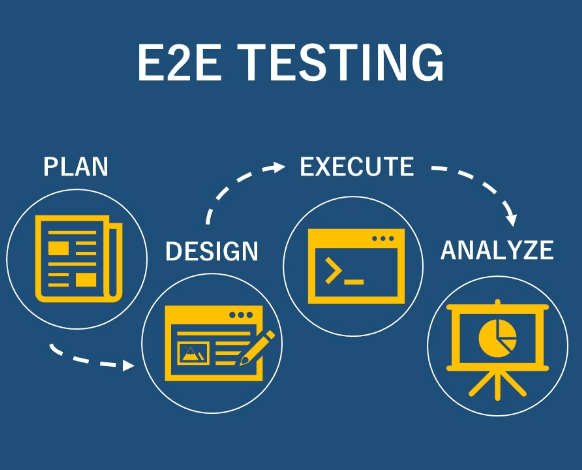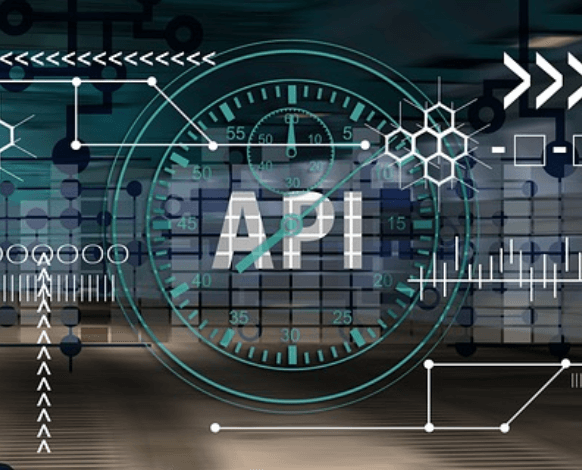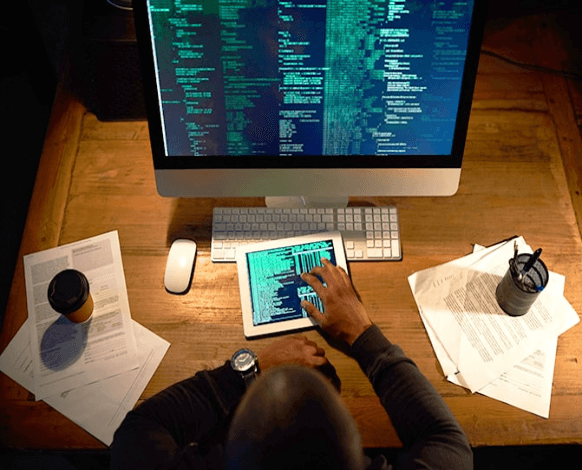WBSとガントチャートの違いとは?作り方やメリットについても解説
COLUMN
最終更新日:2025年04月17日 / 投稿日:2024年06月04日

プロジェクトを管理する際によく使われるツールに、WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構造図)とガントチャートがあります。どちらもプロジェクト全体を個別のタスクとして分け、工程を管理するために使用されるツールです。しかし、WBSとガントチャートは目的や役割が異なり、組み合わせることで真価を発揮します。
この記事ではWBSとガントチャートの違いや作り方、メリット・デメリットについて解説します。プロジェクトマネジメントに関わる方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
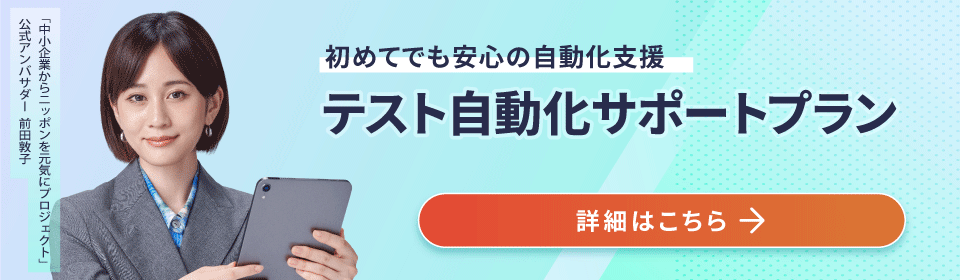
1. WBSとガントチャートの違い

WBSとガントチャートの主な違いは、使用する目的にあります。WBSは、行うタスクを細分化し、すべきことを明確化するために作成します。対してガントチャートは、プロジェクトにおける進捗管理を行う目的で作成されるものです。以下からは、WBSとガントチャートそれぞれの特徴について詳しく紹介します。
1-1. WBSとは
WBSとは、「Work Breakdown Structure(作業分解構造図)」の略称で、プロジェクトを小さなタスクに分解した構成図を指します。プロジェクト全体で必要となる作業を洗い出して細分化し、管理する上で役立つツールです。分解された最も細かなタスクの単位は、ワークパッケージと呼ばれることもあります。
WBSを作成すると、プロジェクトを達成する上で行うべきタスクが明らかになり、プロジェクトチームのメンバーそれぞれが次に何をしたらいいのかが明確になります。その結果、余分な作業を行ったり、作業漏れが発生したりするのを防ぎやすくなるでしょう。
WBSには、プロセス型・成果物型という2つの種類があります。プロセス型は、プロジェクトの計画をベースにタスクを洗い出すものです。成果物型は、最終的に作り上げる成果物をベースに洗い出します。
1-2. ガントチャートとは
ガントチャートとは、プロジェクト管理の際に用いられる表の1つで、計画表・スケジュール表と呼ばれることもあります。20世紀初頭の経営コンサルタントであったヘンリー・ガントが、業務の進み具合を現場監督者が容易に把握できるよう考案したチャートがもとになっています。
ガントチャートでは、プロジェクトを進行する中での段取りを項目別にまとめており、プロジェクト全体の進捗率を一目で把握可能です。また、プロジェクトのマイルストーン(中間目標地点)を管理できる点も、ガントチャートの強みです。チャートにマイルストーンを配置することで、いつまでに何をするべきかがはっきりと分かり、作業の遅れに気づきやすくなるでしょう。
基本的にガントチャートには、縦軸にタスク内容や開始日・終了日、担当者を記載します。横軸には、日時やタスクの進み具合を記すのが一般的です。
2. WBSとガントチャートの作り方

WBSとガントチャートはどちらか片方に頼るのではなく、併用することをおすすめします。WBSは進捗管理ツールではなく、作業工程を洗い出し、細分化・整理する目的で使うツールです。WBSのみでプロジェクトを進めようとすると、現在の進捗状況が確認できず、作業に遅れが発生する可能性があります。
一方で、WBSを作らずにガントチャートを作る場合、担当者の経験からガントチャートにタスクを記載することになります。必要なタスクが抜け漏れていた結果、作業のやり直しや新たなタスクの発生などのトラブルが起こりえるため、正確なガントチャートを作る上でWBSの作成は欠かせません。
WBSとガントチャートを併用すれば、それぞれの強みが生かされ、効率的かつ無駄のない形で計画通りにプロジェクトを進行していけるでしょう。以下からは、WBSとガントチャートそれぞれの詳しい作り方について解説します。
WBSを作成する前に、プロジェクトの実現可能性を評価するフィジビリティスタディを行うことが重要です。
PoCとの違いや進め方については、以下の記事をご覧ください。
フィジビリティスタディとは?PoCとの違いや要素・進め方を解説
2-1. WBSの作り方
WBSを作成する流れは、下記の通りです。
| 1 | 目的・成果物をはっきりと決める |
|---|---|
| 2 | 必要となるタスクを浮き彫りにする |
| 3 | 必要なタスクを細かく分ける |
| 4 | タスクにおける優先度を決める |
| 5 | タスクの工程を構造化する |
まずはプロジェクトを行う目的・作り上げる成果物をはっきりと決めましょう。その後、必要なタスクを洗い出します。ツール開発の場合、「必要な機能をまとめる」「開発を行う」「テストを実施する」といったものが挙げられるでしょう。
タスクを洗い出し終えたなら、各タスクをより細かく分けます。「開発を行う」であれば、「デザインを作る」「プログラミングを行う」といったものに分けられるでしょう。
そして、分割したタスクにそれぞれ優先順位をつけます。「ほかのタスクへの影響度が高く、早く完了する必要があるタスク」については、特に優先度を高く設定するのがコツです。最後にタスク項目を構造化し、重複や漏れがないかをチェックします。
2-2. ガントチャートの作り方
ガントチャートを作成する流れは、下記の通りです。
| 1 | WBSの作成 |
|---|---|
| 2 | タスクの作業時間を見積もる |
| 3 | タスクを行うスケジュールを決める |
| 4 | ガントチャートに入力する |
| 5 | タスクに対してメンバーを割り振る |
まずは、ガントチャートを作る上でベースとなるWBSを作成し、効率的にタスクを洗い出しましょう。浮き彫りになったタスクごとにどのくらいの時間がかかるのかを見積もり、タスクの開始日と完了日を決めます。決定できたら、ガントチャートの作成ツールなどを用いてガントチャートに入力を行います。横軸の色を使い分けると、より見やすくなるでしょう。
最後に、それぞれのタスクを行う人を決定し、記入します。1人への負担が大きいとプロジェクトの破綻にもつながりかねないため、タスクの難易度や量が平等になるよう意識するのがポイントです。
3. WBSとガントチャートのメリット・デメリット

WBSとガントチャートには、メリットもあればデメリットもあります。特徴を知った上で活用すれば、より効率的にプロジェクトを進行できるようになるでしょう。以下からは、それぞれのメリット・デメリットについて徹底解説します。
3-1. WBSのメリット・デメリット
WBSには、以下のようなメリットがあります。
・やるべきタスクを明確にできる
タスクをすべて浮き彫りにし、漏れが生まれるのを防止可能です。
・工数やリソースを見積もりやすい
工数やリソースを予測しやすくなり、プロジェクトを始めてからリソース不足などに悩まされるトラブルが起きにくくなるでしょう。
・タスクの割り振りが楽
タスクそれぞれの内容が明確化され、割り振りを行いやすくなります。
一方で、以下のデメリットには注意が必要です。
・作るのに手間がかかる
タスクを漏れがないよう洗い出し、細分化するのには多くの手間がかかります。
・プロジェクト後半ほどタスクが想定しにくい
プロジェクトの開始前や開始直後の段階で作られるため、後半のタスクは想定が困難です。後半が不透明なことで、後から予想外のタスクが増えるリスクもあります。
3-2. ガントチャートのメリット・デメリット
メリットは以下の通りです。
・プロジェクト全体の進捗を可視化できる
プロジェクトの進捗が視覚化されて一目でチェックできるようになるため、タスクの遅延なども把握しやすくなります。
・誰でも作りやすい
専門知識が不要で、作成の指導を行う必要がありません。無料テンプレートを用いれば、より簡単かつ低コストで作成できます。
以下のようなデメリットもあります。
・タスク同士の関係が分かりにくい
ガントチャートは、「タスクAを終えなければタスクBに取りかかれない」といった関係性を把握するのが困難です。
・アジャイル開発には向かない
短いサイクルでプロジェクトを回す「アジャイル開発」は、計画の変更が定期的に起こります。ガントチャートを使うと、計画変更のたびに何度もチャートを作り直す必要が出てきて非効率なため、向いていません。
タスク間の関係性を明確にするためには、QC7つ道具の活用が有効です。
また、プロジェクト管理においては、品質の確保も重要な要素です。品質マネジメントシステム(QMS)の導入目的や規格について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
QC7つ道具とは?覚え方や新QC7つ道具について分かりやすく解説
QMS(品質マネジメントシステム)とは?|導入目的や規格を解説
ウォーターフォール開発とアジャイル開発の違い|それぞれの特徴も解説
4. ソフトウェア開発におけるテスト工程の重要性
ソフトウェア開発において、テスト工程は納期・品質・コストのバランスを保つために非常に重要な位置づけとなります。特にWBSやガントチャートを用いてプロジェクトの工程を可視化する際には、テスト工程をあらかじめ十分に確保しておくことが、トラブルの未然防止や後工程の効率化につながります。
4-1. テスト工程をより戦略的に進めるために
テスト工程をより戦略的に進めるためには、テスト計画書の作成が欠かせません。テスト計画書には、テストの目的・範囲・実施体制・スケジュール・リスクなどが整理され、プロジェクトメンバー全体で品質保証の方向性を共有するうえで重要な役割を果たします。
テスト計画書の具体的な記載内容や作成のポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
テスト計画書について詳しく解説|目的や記載方法・作成のポイントも
4-2. テスト工程におけるシステムテストの重要性
WBSを作成する際には、単体テストや結合テストだけでなく、システム全体を通して品質を確認する「システムテスト」の工程も明確に組み込むことが重要です。システムテストでは、ユーザー視点での動作確認や非機能要件の検証など、開発の最終段階における品質担保を担います。
テスト全体の中でも規模が大きく、スケジュールに与えるインパクトも大きいため、WBS上でのリソース配分やバッファ設定がプロジェクト成功の鍵となります。
4-3. テスト自動化の導入検討とWBSでの考慮点
テストの効率化を図るうえで、テスト自動化の導入はWBS上でも重要な検討項目です。単体テストやAPIテスト、結合テスト、回帰テストなど、自動化しやすい範囲を見極めて、自動化スクリプトの作成・メンテナンス工程をWBSに明示的に組み込むことで、後の手戻りや人的コストの削減が可能になります。
特に、継続的インテグレーション(CI)を活用して自動テストを繰り返すような開発体制では、テスト自動化の設計段階からスケジュールとリソースを確保することが成功のカギです。
テスト自動化とは?テストの種類と自動化のメリット&デメリット
まとめ
WBS(作業分解構造図)とガントチャートはどちらもプロジェクト管理における重要なツールですが、役割と利用目的が異なります。WBSはプロジェクトのタスクを細かく分け、整理して工数を洗い出す役割のツールです。必要な作業を明確化して、タスクの抜け漏れや無駄な作業をなくす目的で利用されます。
対して、ガントチャートはプロジェクトのマイルストーンを設定し、進捗を管理する役割のツールです。現状どの程度作業が進んでいるかを可視化し、いつまでに何をするべきか、遅れはないか、といった点を分かりやすく伝える目的で使われます。
プロジェクト管理の際には、まずWBSを作って必要なタスクを洗い出し、その上でガントチャートによって進捗を管理するとよいでしょう。
特にテスト工程は品質確保の要であり、テスト自動化も視野に入れた計画・スケジュール管理を行うことで、開発効率と安定性の両立が可能になります。