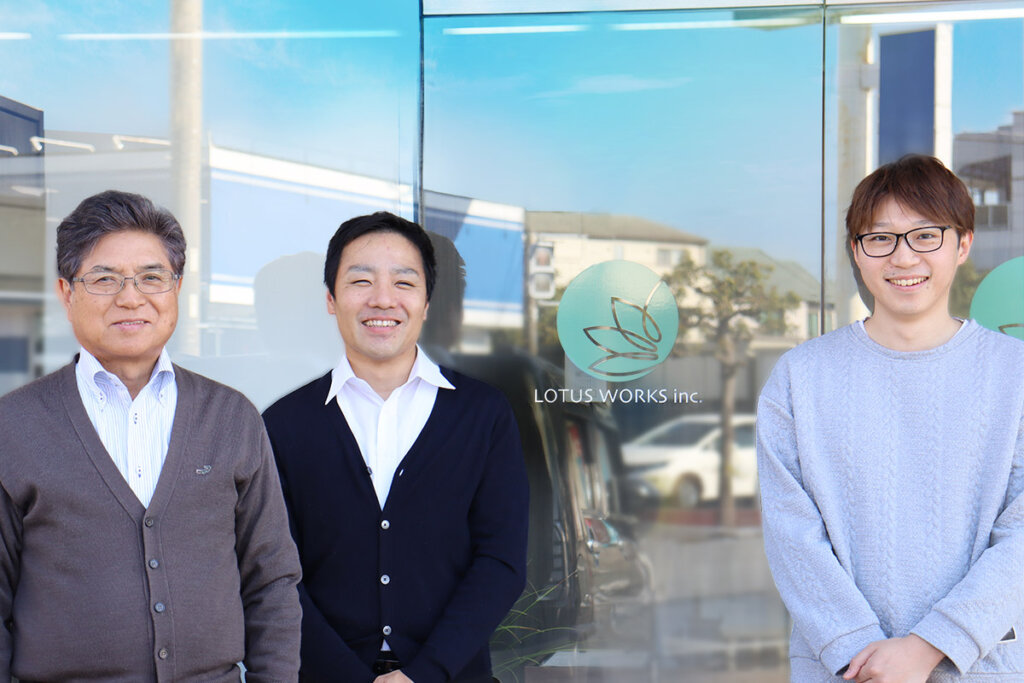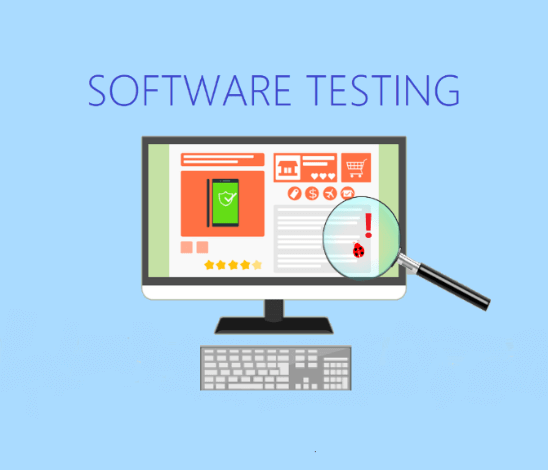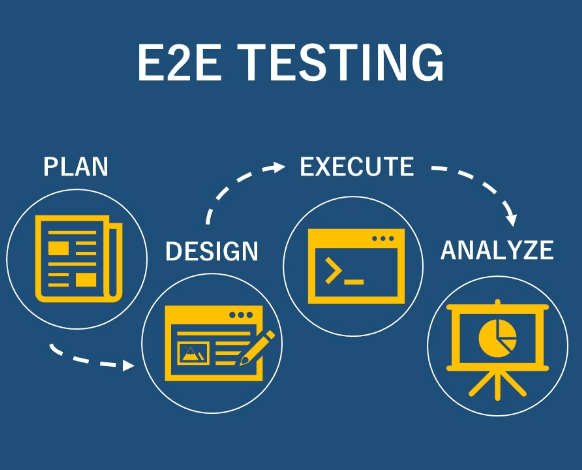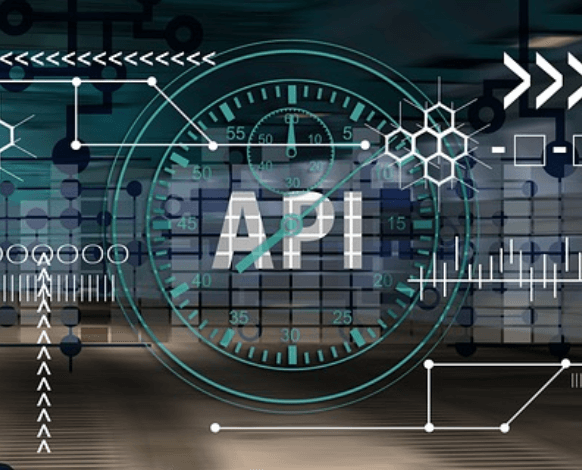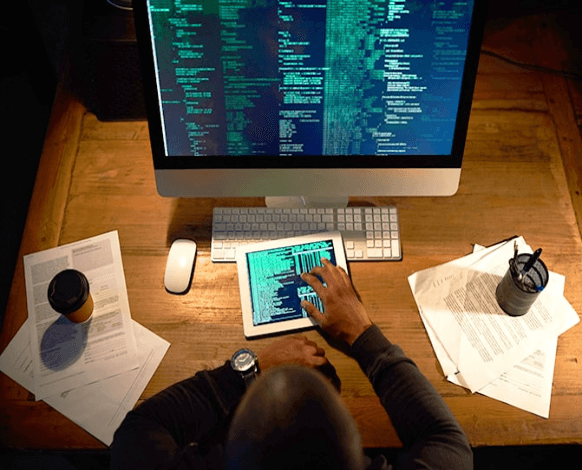ウォークスルーとは?他レビューとの違いから進め方・ポイントまで
COLUMN
最終更新日:2026年02月02日 / 投稿日:2025年10月28日

ソフトウェア開発においては、品質を確保するためにレビューを行い、設計書やコードの不備を早期に発見することが欠かせません。
その中でも、チーム全体で意見を出し合いながらドキュメントの内容を確認する「ウォークスルー」は、教育的効果や理解の共有にも優れた手法として注目されています。
ウォークスルーは、単なるチェック作業ではなく、開発者や関係者が同じ資料を見ながら意見交換を行うことで、ミスの発見と同時にメンバー間の認識をすり合わせるレビュー方法です。開発の品質向上だけでなく、チーム全体のスキルアップにもつながります。
そこで今回は、ウォークスルーの基本概要や他のレビュー手法との違いから導入のメリット・デメリット、さらに具体的な進め方や実施ポイントまで詳しく解説します。
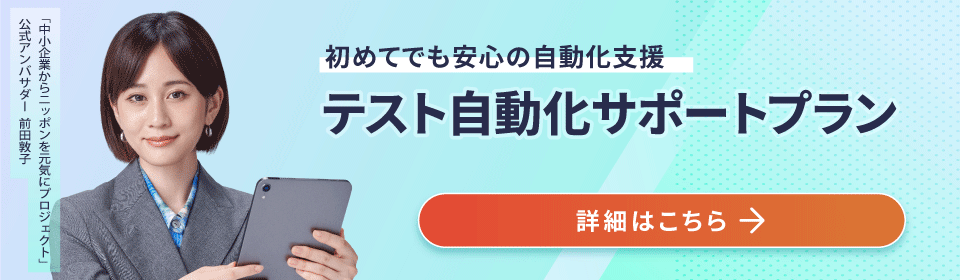
1. ウォークスルーとは?

ウォークスルー(Walk through)とは、 ソフトウェア開発の工程で作成された設計書や仕様書、ソースコードなどの成果物を開発チーム内で確認・評価し、意見の交換や承認を行うレビュー手法の1つ です。
基本的に成果物の開発者本人が主体となって資料の内容を説明し、「レビューア」と呼ばれる参加メンバーがその内容を確認していく形式で行われます。開発物における欠陥の発見と対処の議論が主な目的で、正式な議事録を取らずカジュアルに進行されることが特徴です。
そもそもソフトウェア開発におけるレビューとは、 開発工程の中で成果物を第三者が確認し、エラーや仕様の矛盾などを未然に防ぐための、いわば「品質保証活動」 です。テスト工程に進む前の段階でレビューを実施することで、バグ修正の工数やコストを大幅に削減できるほか、後工程での手戻り防止にもつながります。
数あるレビュー手法の中でもウォークスルーは、メンバー間の理解共有や教育効果が重視される傾向にあります。参加者は自由に意見や質問を出し合いながら、資料の妥当性や改善点を検討します。これにより、単なる不具合検出だけでなく、チーム全体のスキル向上や設計意図の共有にも貢献するでしょう。
2. 開発過程におけるウォークスルー以外のレビュー手法|違いも紹介!

ソフトウェア開発におけるレビューには、ウォークスルー以外にも複数の手法があります。
いずれのレビュー手法も品質向上や不具合の早期発見を目的とする点は共通していますが、参加者や進め方、形式の厳密さにはいくつかの違いがあります。
ここからは、代表的な3つのレビュー手法である「インスペクション」「パスアラウンド」「テクニカルレビュー」について、それぞれの特徴とウォークスルーとの違いを紹介します。
2-1. インスペクション
インスペクションとは、プロジェクトの当事者ではない第三者が、事前に定められた評価基準に基づいて成果物を検証する公式なレビュー方法 です。設計書やソースコードに潜む欠陥を正確に洗い出し、品質保証や開発プロセス全体の改善につなげることを目的としています。
インスペクションの特徴は、プロセスや役割分担が厳密に定められている点です。モデレーター(進行役)、記録係、レビューアなどの役割を明確にし、チェックリストを用いながら体系的に検証を進めます。また、レビュー結果は不具合表にまとめられ、分析・フィードバックまでを正規のプロセスとして管理します。
ウォークスルーとの大きな違いは、公式性と厳密さにあります。ウォークスルーでは開発者自身が説明を主導し、参加者が自由に意見交換を行うのに対し、インスペクションは第三者が中心となって進行します。チェックリストや記録の使用が必須で、工程移行やリリース判定など、品質保証の重要な場面でよく用いられる形式的なレビューです。
2-2. パスアラウンド
パスアラウンドとは、成果物を複数のレビュアーに配布し、それぞれが個別に内容を確認・コメントする方式のレビュー で、「非形式レビュー」とも呼ばれます。対面での会議を行わず、メールやクラウドを通じて意見を集約するため、時間や場所を問わず柔軟に実施できる点が特徴です。
パスアラウンドの主な目的は、第三者の視点から成果物の品質を評価し、バグや仕様漏れを早期に発見することにあります。特にリモートワーク環境や多拠点チームなど、リアルタイムでの打ち合わせが難しい場合に有効です。
ウォークスルーとの違いは、コミュニケーションの形式にあります。ウォークスルーは参加者が同席して説明・意見交換を行うのに対し、パスアラウンドは非同期的に進むため、議論の深さや即時性には欠ける傾向があります。
2-3. テクニカルレビュー
テクニカルレビューとは、設計書やソースコードなどの技術的な妥当性を確認し、実装品質や設計精度の向上を図るレビュー手法 です。アーキテクチャ設計や外部インターフェースの仕様検討といった技術的判断が重要な工程で活用されることが多く、専門知識を持つエンジニアが中心となって実施します。
テクニカルレビューは議論や合意形成を重視する点が特徴で、モデレーターが議事を進行し、議事録を残しながら技術的な課題を整理します。単なる誤りの発見ではなく、「より良い設計・実装をどう実現するか」が主な議論の目的となります。
ウォークスルーとの違いは、レビューの焦点にあります。ウォークスルーが主に文書全体の理解共有や軽微な不備の発見に適しているのに対し、テクニカルレビューは専門技術の観点から設計や実装の妥当性を深く検証します。そのため、参加メンバーには高い専門性が求められ、技術力向上や品質保証の両面で効果を発揮するレビュー手法と言えるでしょう。
3. ウォークスルーを導入するメリット・デメリット

ソフトウェア開発においてウォークスルーを導入することには、メリットとデメリットの両面があります。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
ウォークスルーの最大の利点は、誤りの発見に加えて、チーム内の理解や協働を促進できる点にあります。一方で、ウォークスルーはチーム全員の積極的な参加があってこそ効果を発揮することから、形式的に実施するだけでは期待する効果が得られない可能性もゼロではありません。
とは言え、 これらのデメリットは進め方を工夫することで改善できます。 意見を出しやすい雰囲気づくりや記録体制を整備することで、単なるレビュー手法にとどまらず、チームの成長を支える重要なプロセスとしても機能するでしょう。
4. 【3STEP】ウォークスルーの進め方と実施ポイント

ウォークスルーを効果的に実施するためには、事前準備からレビュー後のフォローまで、一連の流れを整理してから進めることが重要です。
最後に、ウォークスルーの進め方を3つのステップに沿って紹介するとともに、実施時のポイントもあわせて解説します。
4-1. STEP(1)レビューアの選出と資料の準備
ウォークスルーを実施する際は、まずレビューの目的を明確にした上で、目的に応じた適切なレビューアを選定します。
確認したい観点(仕様の漏れ、設計の妥当性、機能の使いやすさなど)に応じて、 プロジェクト内容に精通したメンバーを選ぶことが重要 です。レビューアは最大7名程度が推奨されており、管理者はあえて招かずに活発な意見交換を促すケースもあります。
資料はレビュー対象のドキュメント、データフロー図、コードなどを含め、レビュー数日前にはレビューアに共有します。背景や概要を補足資料として用意することで、全員が同じベースラインに立ち、議論が活性化しやすくなります。 ボリュームが多い場合は、区切りの良い単位に分割し、なるべく1時間以内に収めるのが理想 です。
4-2. STEP(2)レビュー・ミーティングの実施
ミーティングでは、作成者が資料を読み上げながら説明し、レビューアからの質問や指摘を受け付けます。ポイントは、 発言しやすい少人数で実施すること、実施範囲を絞って短時間で行うこと、そして粗探しをせず建設的な議論を心がけること です。
章ごとに質問タイムを設けると議論が活性化しやすくなります。深い議論によってミーティングが長引く可能性がある場合は一旦区切り、宿題事項として持ち帰るのも良いでしょう。
Webミーティングではチャットやリアクション機能を活用すると、発言しやすい雰囲気づくりにつながります。判明した課題はその場で保留リストに追加し、最終判断は上長やクライアントとのすり合わせ後に行います。
4-3. STEP(3)指摘事項の記録・対応と最終確認
ウォークスルーでは正式な議事録は必須ではありませんが、指摘事項や決定事項はリアルタイムで記録します。 成果物の開発者が書記を兼任する場合もありますが、別メンバーが担当すると進行がスムーズ です。最近では、共同編集可能なドキュメントや自動議事録作成ツールを活用する方法もあります。
レビュー終了時には、作成者が修正点や宿題事項を読み上げ、参加者全員で最終確認します。さらに、管理者や参加できなかったメンバー向けに報告書を作成・展開し、議論内容や修正事項を共有することで認識のズレを防ぎます。このステップを踏むことで、 ウォークスルーの効果を最大化し、開発成果物の品質向上につなげることが可能 です。
まとめ
ソフトウェア開発におけるウォークスルーは、成果物の欠陥を早期に発見し、チーム内で認識を揃えるためのレビュー手法です。作成者が資料やコードを読み上げ、レビューアと建設的な議論を行うことで、ドキュメントや設計の品質向上につながります。
しかし、ウォークスルーは人的な確認が中心のため、効率や網羅性には限界があります。より効率的に品質向上と開発スピードの両立を実現するためには、テスト自動化ツールの導入もおすすめです。ウォークスルーとあわせてテスト自動化ツールの導入も検討している方は、ぜひローコードで簡単に操作できる「ATgo」にお問い合わせください。