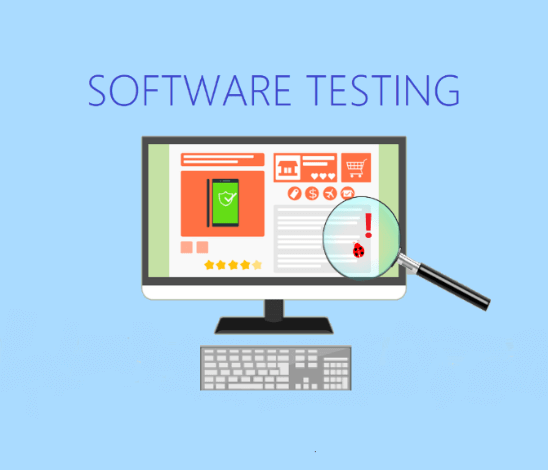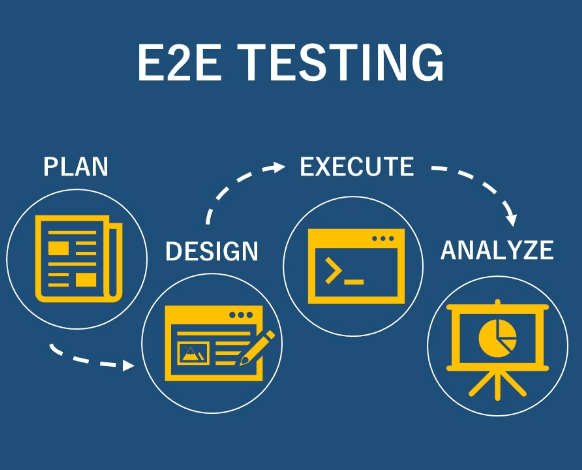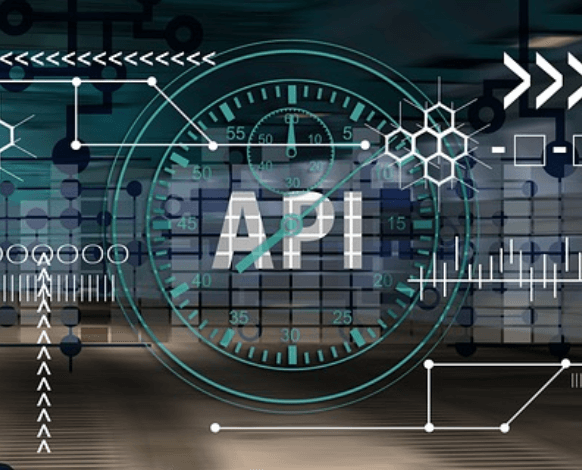リグレッションテストとは?実施目的や自動化のメリット・注意点も
COLUMN
最終更新日:2026年02月03日 / 投稿日:2022年08月31日
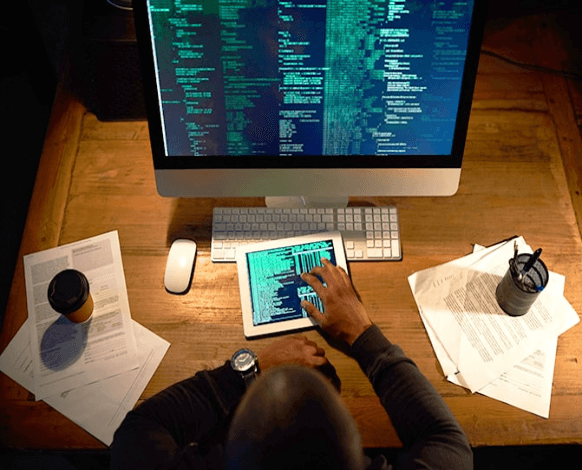
システム開発のプロジェクトに携わると耳にするリグレッションテストは、システムの品質を保つ重大な役割を担っています。何度も繰り返し行われることが多く、作業工数とコストがかかります。そのため、「品質を保ったままテストの負担を軽減したい」と思う方は多いのではないでしょうか。
そこで今回では、リグレッションテストの概要や省略することで起こるリスク、効率よくテストを実施するポイントを紹介します。
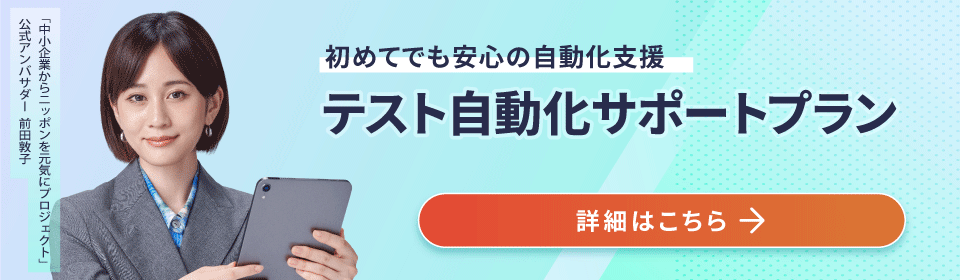
目次
1. リグレッションテストとは?

リグレッションテストとは、バグなどの不具合が発生し、プログラムの一部を修正した後に、プログラム全体が正常に作動するか確認するテストです。別名「回帰テスト」や「退行テスト」とも呼ばれています。
リグレッションテストの目的は、顧客の仕様書通りのシステムを確実に納品することです。
プログラムとは、システムを動かす指示書のことです。プログラムの一部を変更すると、新たに別の箇所でバグが発生し、システムに指示が通らなくなることがあります。プログラムを変更する場合は、影響範囲を確認し、必ずリグレッションテストを実施する必要があります。
リグレッションテストは品質保証に欠かせない一方で、実施には膨大な時間と工数がかかります。
そのため、テスト自動化による効率化が大きな注目を集めています。
実際に、ある企業ではレグレッションテストの工数を大幅削減し、しかも導入のしやすさを重視したスムーズな移行を実現しました。
詳しい事例は以下をご覧ください。
「レグレッションテスト25時間→3時間で約88%減」テスト自動化ツールATgo導入事例
1-1. リグレッションテストとデグレードテストの違い
リグレッションテストの実施時に使われることがある用語に「デグレードテスト」があります。
デグレードテストとは、プログラムの変更や修正によってシステムが機能低下していないかを確かめるためのテストです。デグレード(degrade)は「劣化する」「低下する」を意味し、IT業界ではシステムの機能低下や正常に動作しない状態を指します。
デグレードテストとリグレッションテストは、どちらもプログラムの変更・修正がシステムの機能低下につながっていないかを検証するテストであり、基本的には同義です。デグレードテストという言葉を聞いたときには「リグレッションテストのこと」と考えるとよいでしょう。
なお、世界的なソフトウェアテスト資格であるJSTQBのシラバスでは「リグレッションテスト」「リグレッション」で統一されています。業務上は「リグレッションテスト」を用いたほうがチーム内で通じやすいでしょう。
出典:JSTQB認定テスト技術者資格「シラバス(学習事項)・用語集」
1-2. リグレッションテストを実施するタイミングと目的
システム開発は、プログラムを機能ごとに区切って作成する方法が一般的です。作業が進むごとにさまざまなテストで検証を行います。
テストの大まかな順番は以下の通りであり、リグレッションテストを実施するタイミングは、各テストの終了後です。
(1)単体テスト
プログラム単体が完成した後に、問題なく作動するかを確認するテストです。新しく修正したメソッドが他のメソッドに悪影響を与えていないかを確認するために行います。
単体テストとは?メリット・デメリットと手法から3つの注意点まで
(2)結合テスト
単体テストが終了した各プログラムを結合した結果、プログラム同士が連携して作動するか確認するテストです。新しい機能が他のシステムとの連携に悪影響を与えていないか確認するために行います。
(3)総合テスト(ST:システムテスト)
本番同様の環境を使用し、完成したシステムを運用することでシステム全体が問題なく作動するか確認するテストです。システム全体の流れが新機能によって壊れていないかを確認するために行います。
リグレッションテストは、「変更点だけでなく、周辺機能や関連システムも含めて確認すること」がポイントです。
テストでの検証が不十分だと、さまざまな箇所でデグレーションが発生します。各段階で正確なテストを実施し、品質を保つことが大切です。
2. リグレッションテストは省略NG!省略した場合の2つのリスク

テストの時間が確保できない、工数がかかり予算が足りないなどの理由で、テストの省略が検討されます。納品後に不具合が発生した場合は、顧客の信用を損なうため省略しないほうがよいでしょう。
ここでは、リグレッションテストを省略することで発生する2つのリスクを解説します。
2-1. 顧客との信頼関係が崩壊する
リグレッションテストを行わず、デグレードを残したまま納品すると、「画面が表示されない」「入力できない」など、さまざまな動作不良が発生するおそれがあります。動作不良が発生したシステムは本来の使用目的を達成できなくなり、顧客の業務が停止する可能性もゼロではありません。デグレードが利益損失につながった場合、顧客の信頼関係が崩壊します。
また、デグレードの内容がセキュリティにかかわる場合は、システムの脆弱性を放置するおそれもあります。例えば納品後に不正アクセスや情報漏えいなどのセキュリティ事故が発生するケースが考えられるでしょう。顧客側に大きな被害が発生し、信用が失墜するリスクがある点に注意してください。
本来実施すべきテストを怠ったことが原因で不具合が発生すると、顧客は手を抜いて仕事をされたと感じ、新規のバグが発生することより悪い印象を抱く場合があります。最悪のケースでは、仕事の打ち切りや次の仕事をもらえなくなる可能性もあるでしょう。
不具合により期限までの納品が厳しい場合は、早めに顧客へ事実を説明することが大切です。
2-2. 余分なコスト・工数が発生する
デグレードが発生したシステムは再改修が必要です。
一般的に、システムの不具合は早期発見できるほど原因特定がしやすく、修正の範囲や工数を抑えることができます。効率的に業務を進めるには、不具合の早期発見・早期対応をすることが重要です。
しかし、システム開発が完了した後に改修する場合は、発生している不具合の影響が広範囲に及んでいる可能性があります。大きな影響範囲の中から不具合の原因を特定する必要があり、原因特定から解消までに多くの時間と労力がかかります。
リグレッションテストの省略によって工数、コスト削減を図ったはずが、発覚したデグレードへの対応でさらなる作業工数とコストがかかるケースもあるでしょう。
顧客のクレームや補償への対応も必要となることを踏まえると、リグレッションテストは可能な限り実施するべきと言えます。
3. 【3STEP】リグレッションテストの実施範囲・項目の決め方

範囲・対象を絞り込まずに行うリグレッションテストを「フルリグレッションテスト」と言います。
本来、どのテスト工程においてもフルリグレッションテストを行うことが理想です。しかし、規模が大きいシステムでフルリグレッションテストを実施すると時間やコストの負担が膨大になってしまい、現実的ではありません。
そのため、リグレッションテストの範囲・項目はいくつかのポイントで優先度を付け、ある程度限定した内容で実施するのが一般的です。
ここからは、リグレッションテストの実施範囲・項目の決め方を3つのステップに分けて紹介します。
3-1. STEP1:バグの影響を受ける箇所の把握
まずはテストの正確な範囲を決めるために、バグが発生したときに影響を受ける箇所を把握します。影響を受ける範囲が狭いとデグレーションを見落とす可能性が高まり、反対に範囲が広すぎると作業工数が増加するため、慎重に行いましょう。
影響を受ける箇所と、関係するデータを扱う箇所を中心にリグレッションテストをすることで、不要な作業工数を削減し、業務を効率化できます。確認範囲の特定により適切な修正が可能になり、品質向上も期待できるでしょう。
3-2. STEP2:部分別のリスクレベルの把握
バグの影響を受ける箇所を確認したら、次にデグレーションが発生した場合のリスクレベルを把握します。リスクレベルは、システム内にある変更前のプログラムの影響範囲が広いほど高く、影響範囲が一部など限定的な場合は低いと判断できます。
例えば、システムの土台となるプログラムやコードを変更すると、影響を受ける範囲が広く、デグレーションのリスクが高いと言えるでしょう。一方、システムの一部を構成するモジュールの変更は、全体への影響力が弱くリスクが低いと考えられます。
事前に不具合の箇所とリスクレベルを把握することで、テストに優先順位をつけ、効率的な作業が可能です。
3-3. テスト項目の優先度決定
プログラムの変更が影響する範囲と、デグレードが起きた際のリスクレベルが高い箇所を把握した後は、テスト項目に優先度を付けます。
テスト項目の優先度は、過去の不具合の傾向を分析して検討します。優先度が高い項目を抜き出したら、リグレッションテストの条件や手順などをまとめたテストケースを作成しましょう。
優先度が高い項目は基本的に、ユーザーが操作をする画面や、ユーザーの情報を管理する機能が該当します。例えば予約システムのリグレッションテストであれば、テストケースは会員登録・ログインや予約受付、決済、リマインドといった重要な機能に絞ることがおすすめです。
優先度が高い項目でテストケースを作ることで、リグレッションテストにかかるコストを低く抑えつつ、顧客のビジネスに大きく影響する不具合の見逃しを防げます。
4. リグレッションテストを実施する際のポイント

リグレッションテストを実施する際は、不具合の抜け漏れがないようポイントを押さえることが大切です。
以下では、リグレッションテストを円滑に実施するためのポイントを紹介します。リグレッションテストの進め方に悩んでいる方は、3つのポイントを実践するとよいでしょう。
4-1. 繰り返し実行し徐々にテストケースを拡張していく
ソフトウェアテストの7原則の1つに、同じテストの繰り返しは効果が薄くなるという「殺虫剤のパラドックス」があります。
しかし、リグレッションテストは殺虫剤のパラドックスには当てはまりません。リグレッションテストを繰り返し実行すればデグレードの発生率が低減し、システムの信頼性向上につながるためです。
また、リグレッションテストを繰り返し実行する際は、徐々にテストケースを拡張しましょう。段階的なテストケースの拡張は、プログラムの変更範囲が増えることに伴うデグレードの発生にも対処しやすくなります。
4-2. すべてのテストレベルで実行する
プログラムの変更や修正は、軽微な内容であってもシステム全体に影響を及ぼす可能性があります。デグレードがどの範囲で起きているかを見逃さないよう、単体テスト・結合テスト・システムテストのそれぞれでリグレッションテストを行いましょう。
すべてのテストレベルでリグレッションテストを実行すると、デグレードの早期発見から対処につなげられます。影響範囲が小さいうちにデグレードを発見することが、効率的なリグレッションテストのコツです。
4-3. できる限り早い段階で自動化を進める
リグレッションテストを手動で繰り返すのは非常に時間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも伴います。そこで効果的なのがテスト自動化です。
テスト自動化とは、テスト自動化ツールを導入して各種テストを自動的に進めることを指します。リグレッションテストは同じテスト内容の繰り返しが多く、テスト結果が「成功 or 失敗」のシンプルな判定である点が、テスト自動化に向いている理由です。
リグレッションテストを自動化すると、テストは高速かつ正確に行われます。その間に開発者は新機能の実装や改善に集中できるため、プロダクトの品質向上だけでなく、チームの飛躍的な生産性向上も実現可能です。
また、リグレッションテストを単体テストの段階から導入していれば、デグレードの効率的な発見にもつながります。導入したテスト自動化ツールは次回のリグレッションテストでも使えるため、将来的なリグレッションテストの効率が向上することも期待できるでしょう。
なお、テスト自動化を進める際はツールの選定や導入に時間がかかる場合もあります。プロジェクトの初期段階からテスト自動化をするには、できる限り早い段階で導入を進めることが大切です。
テスト自動化なら「ATgo」におまかせ!
Webアプリケーションのテストをもっと簡単・効率的にしませんか?
ATgoはローコードで簡単に操作できるWebアプリケーションテスト自動化ツールです。これひとつでUIテスト・APIテストの実行と比較検証を自動化。システム開発における工数削減と品質確保をサポートします。
- 初心者はノーコードで、プロはスクリプト編集であらゆるテストケースに対応可能
- セキュアなテスト環境にも素早く簡単導入
- ワンクリックでテスト実行&エビデンスを自動収集
- スクリプト生成AI機能やAI画像比較機能でもっと便利に
- 日本の現場にフィットする安心の国産ツール
リグレッションテスト等で大きな効果を発揮
初回に作成したスクリプトを再利用することで、テストを実行すればするほど効率化。手動テストに比べてコスト・工数の削減が可能です。インストールなしでご利用いただけるので、素早く簡単に導入できます。ATgoでWebアプリケーションテストの効率化を今すぐお試しください。
5. リグレッションテスト自動化の主なメリット5選

リグレッションテストはプログラムの変更を行ったときに実施したほうがよく、自動化することには多くのメリットがあります。リグレッションテストに課題を感じている方は、自動化によって自社の課題が解決できるかを検討してみてください。
最後に、リグレッションテスト自動化による主なメリットを5つ紹介します。
5-1. 作業効率が向上する
リグレッションテストで推奨されているテストの繰り返しは、自動化すれば手動で行う必要がありません。繰り返し作業に充てる人員・時間を削減できて、作業効率が向上します。
また、自動化によって大量のテストケースも短時間で処理できるため、テスト実行のスピードアップも図れます。
5-2. 品質が安定化する
リグレッションテスト自動化を進めると、手動テストで発生しやすい「分岐条件の見逃し」といったヒューマンエラーを排除できます。ヒューマンエラーの排除はデグレードの防止につながり、テスト品質の安定化が可能です。
さらに、テストの手順や操作の一貫性を確保できるため、テストを繰り返しても安定した結果が得られる点もメリットです。
5-3. コスト削減につながる
テスト自動化ツールの導入には初期投資が必要となるものの、繰り返しのテスト作業を削減すればトータルコストを下げられます。テスト担当者が他の重要な作業に集中できるようになり、人的リソースの最適化も図れるでしょう。
予算やテスト時間の確保といった課題を解決することで、リグレッションテストを省略せずに繰り返し実行できる環境が整います。
5-4. 不具合の早期発見につながる
リグレッションテスト自動化は、継続的インテグレーション(CI)との高い連携を発揮できるメリットがあります。コードが変更されるたびに自動テストを実行でき、不具合を早期に発見可能です。
加えて、バグ修正が早くなることで結果的に開発サイクル全体のスピードも向上します。リリーススピードの向上は、顧客満足度を高められるポイントです。
5-5. テストカバレッジが向上する
手動のリグレッションテストでは、多くのテストケースを実行するには手が回らず、隠れたバグに気付かない可能性があります。リグレッションテストを自動化すると手動では手が回らない多くのケースをテストでき、テストカバレッジ(テストの網羅率)が向上します。
また、毎回の変更時に自動でテストを実行することで、リグレッションリスクを最小限に抑えられます。
6. リグレッションテスト自動化の注意点

リグレッションテストを自動化することには、メリットだけでなくいくつかの注意点も存在します。
● 変更点が多いテストは自動化に向いていない
● 自動化ツールの導入時や運用にもコストがかかる
● 手動テストと自動化する領域を見極めが成功のカギ
自動化ツールは、登録したテストプログラムの内容しか作業ができません。変更が頻繁にあるテストは、プログラムを書き換える手間がかかり、工数削減の効果が弱まります。そのため、すべてのテストを自動化することは難しいです。
自動化ツールは適切に使用すると便利ですが、導入時だけでなく運用やメンテナンスにもコストが発生します。実際に削減できるコストと、自動化ツールを導入するコストを比較して検討する必要があります。重要な部分を自動化しつつ、人間の目で確認すべき領域を見極めることが成功のカギです。
テスト自動化とは?テストの種類と自動化のメリット&デメリット
まとめ
システム開発にはバグや不具合の発生がつきものです。改修を行った後に、システム全体が正常に作動するかを確認するリグレッションテストは、重要度が高い作業と言えます。
納期に余裕がないなどの理由でリグレッションテストを怠ると、顧客との信頼関係が損なわれる事態につながりかねません。リグレッションテストを省略すると、さらなる工数とコストがかかる場合がほとんどです。
リグレッションテストは省略せず、テストする範囲を絞ったり、開発工程からテスト自動化ツールの導入を計画したりして、効率よく進めましょう。